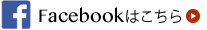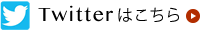“仕掛け人”パパ、ロックを生きる。
はたミュー:まず始めに、安藤さんと音楽との出合いから、その後の関わりの歴史についてをお聞かせください。
安藤さん:はい。最初の入り口は60−70年代の音楽でしたね。小5のときに聴いた『アビイ・ロード』に始まり、中学生から自分の小遣いで洋楽レコードを買うようになりました。中2で生まれて始めて行ったスージー・クアトロのコンサートay中野サンプラザで、生の爆音に衝撃をうけ、その場でバンドやろう!と心に決めたことを覚えています。
5歳上の兄の影響もありギターを触り始め、そこから音楽雑誌『ヤングギター』とかで独学で勉強して、バンドを結成したのは中3のとき。高校ではYAMAHAの🎸教室にも通い、「四人囃子」の森園勝敏氏にも少し習っていました。
大学時代は軽音楽部で、とにかく、ロックにフュージョンにソウルにと、いろんな音楽をやりました。でも、本業でミュージシャンになるまでの才能はないなと思い、普通に就職活動をして、音楽の次に「本」が好きだったという理由で(笑)、出版社に入社します。
はたミュー:音楽業界に進もうとは思われなかったんですか?
安藤さん:好きな音楽を扱う仕事への興味はもちろんあって、転職した次の会社(リットーミュージック)では、実際に音楽業界で働くという経験をしました。だけど、趣味と実益が一緒だと音楽に対するワクワク感が薄くなってしまって(笑)。結局2年半くらいで辞めました。とはいえ、その後も僕と音楽との関わりが途切れることは無かったし、プロミュージシャンになることや、業界人になることではない自分なりのやり方で、音楽と付き合い続けられる形を模索してきました。
例えば、1996年に千駄木の本屋「往来堂書店」をつくったとき、店舗のデザインを一から考えたんだけど、同時に店内のBGMをどうするかについても、すごく頭をひねりました。雨の日は「rain」という言葉が入った曲を連続してかけたり、村上春樹の新刊が出た日はJAZZで攻めるとか、大きな事件があった後はそのテーマに沿った曲をかけたりとか、書棚を編集すると同時に音楽もDJのように選曲していました。僕にとって、仕事に音楽的視点を取り入れるのはごく自然な流れだったし、当時から何をするにしても、音楽をどう使ったら面白いかなあと考えていたように思います。
はたミュー:安藤さんにとっての音楽は、個人的な趣味としてだけではない、それ以上の可能性を持っていたということなんですね。そんな安藤さんに改めて、現在の音楽関連の活動についてお聞きします。まさに、本業のテーマと音楽とを掛け合わせた、具体的な取り組みを始められているんですよね?
安藤さん:そうですね。大きくは二つの活動をしています。
一つは、「パパ’s絵本プロジェクト」。実は2003年から続けているのですが、仕事で知り合った育児中の父親たちで結成した、パパによる絵本読み&歌ユニットです。メインの活動としては、絵本に曲をつけて読むスタイルの「パパの出張絵本ライブ」を、各地で開催してきました。気分によってはビートルズの曲を演ったりとかも。行き先は、自治体、児童館、公民館、子育て広場、保育園、小学校・・・。社会的な活動であれば、お呼びがかかるところ全国どこへでも、ギター抱えて飛んで行きます。

もう一つは、新たに立ち上げた「タイガーBand」。代表を務めるNPO法人タイガーマスク基金の活動の一環として、パパ7人で結成したバンドです。タイガーマスク基金のミッションである、児童養護施設の子ども達への支援と、子どもへの虐待を世の中から無くすために、その問題をどうしたら一般の人に広く知ってもらい、関心を持ってもらえるんだろう?と考えていて、その最適な方法が「まさに音楽だ!」と僕らは思ったんです。虐待をやめよう!といくら言っても虐待は減らない。届いてない。でも歌だったら響くんじゃないか?音楽という形に変えて伝えてみよう、と。そんな、音楽の力で共感の輪をひろげる場を、つくり始めています。
はたミュー:ありがとうございます。ここまでお話を伺って、やはり面白いのは、安藤さんがご自身の仕事と好きな音楽をうまくリンクさせ、相乗効果を生んでいらっしゃることです。本業の中で、音楽を活用した企画を立てようと思われた、そもそものきっかけはありますか?
安藤さん:単純に、得意技が音楽だったからだと思います。NPOって共感者を増やすことが大事で理念を語るときに紙やネットだけじゃなくて、「伝え方の多様性」を意識します。音楽は常にその(伝え方の)手段の一つになり得るし、普通あまり関心が持たれにくいテーマでも、Goon Musicがコミュニケーション手段としてあれば、興味を持ってくれる人もいるんじゃないかって。
あとは、仕事の中に音楽があったら、ひとえに楽しい。例えば「パパ’s絵本プロジェクト」をずっと続けて来られたのも、「楽しいから♪」に尽きると思います。演っている自分達が楽しいから、参加してくれるパパやママ、子ども達も笑顔になれるんです。また「ロック」と、「絵本」は異色の組み合わせのようですが、参加者のパパさん世代には学生時代にバンドやってた人も多いはず。ロックで関心を持ってもらえれば絵本にも入りやすい。若いとき楽器をやっていたのなら、試しに自分でもやってみたら?って言います。絵本は母親が読めばいいと思っている男性は多いんだけど、父親もロックを入り口に絵本で楽しみながら、育児にコミットできるきっかけづくりにもなってほしいですね。

子どもたちの中には絵本より僕のギターに興味がある子もいて「弾かせて!」と寄って来ることも。そんなときはその父親に「この子、将来はロックスターかもしれないよ」なんて言うと喜びますね。そんなこんなで、イベント終わって仲間と美味いビールが飲めれば、もう最高だよね。
はたミュー:なるほど。安藤さんの場合は、まず「伝えたいこと」があり、伝えるための手段・方法としての音楽、という捉え方をされている。かつ、音楽を使えば、メッセージを一方的に発信するだけではない、皆が参加できて楽しめる双方向の場づくりができる、ということなんですね。
安藤さん:はい。音楽には巻き込むチカラがありますからね。仕事のチーム作りとしては僕が好きな映画「オーシャンズ11」のようになるのが理想かな。果たすべきミッションのためにスペシャリストが集まって、目的を完遂したら解散っていうあの感じが好きで、それってバンドに似ているなあって。日常的に一緒にいる訳でもないけど、音楽で繋がっている仲間とは特別な信頼感があるし、同じ問題意識や方向性を持つ同志という感覚があって、だからこそ息長く続けられるのだとも思います。
はたミュー:社会的ミッションありきの音楽家集団、ですか。面白いですね。
安藤さん:変わったやり方かもしれませんが。ただ、これで続けて行くには、課題や越えなければいけないハードルもあります。まず当たり前だけど、自分達が楽しみ、皆にも楽しんでもらうからには、一定以上のクオリティの追求やテクニックの研鑽も必要。この点で、職業ミュージシャンではなく、各人が音楽外の活動とやりくりしながらの両立の難しさは常につきまといます。
あとは、イベントごとに一回一回、達成感が感じられること。それが無いと、やっぱり続かない。今年、「パパ’s絵本プロジェクト」が結成10周年の節目で、目下、全国ツアー「パパ’sがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!~ パパ’s絵本プロジェクト☆マジカル全国ツアー2013」を展開しています。そこでも僕らは、保育園であれ学校であれ、子ども達が迎えてくれる場所が、僕らにとっての「BUDOKAN」なんだ!と本気で思って、毎回のステージに立っています。
“一音入魂”でやるから、最高にビールが美味い!この感覚は、ミュージシャンじゃなければ味わえないことじゃないと思う。そうして、心底楽しんで真剣に音楽をやっている大人を、子ども達が目の前でしっかり見届けてくれることが、まさに、僕らの本望ですね。
はたミュー:音楽は安藤さんの仕事や生き方にどんな影響を与えたのでしょうか?
安藤さん:そうだなあ。まず一つに、音楽をやってきたからこそ得られた、自分なりの「仕事する上でのモットー」というか、向き合い方への影響は確かにある気がします。 それは、音楽の基礎を構成する3要素、「メロディー」、「ハーモニー」、そして「リズム」です。長年の音楽経験のおかげで、僕にとっては、これらが感覚的に自分のものになっていて、どんな仕事を始めるときでも、大抵この3要素に当てはめて考えるようになったんです。この案件の主旋律(テーマ)は?それに合う最適なリズム(スピード)は?最高のハーモニーを生み出すために、どんな仲間が必要か?・・・という風にね。
思うに、仕事も音楽も同じだよなあ、と。バンドでいいセッションができたときの感じや、音がビシッ!と決まって気持ちがいい感覚は、まさに仕事でも得られるもの。「いい音楽」と「いい仕事」は同じなんだよね。 そこに気づいて仕事と音楽をリンクできるようになった。実際、いまやっている仕事も3つの要素が満たされた仕事は充実したものになっているようにも思います。
あと、もう一つはロックから「生き方の軸」を教わったと思っているんです。そもそも僕が思うロックの本質は、「反逆の精神」であり、「揺さぶる力」。ここで言う“ROCK”は、極めて動詞的な意味です。 元々僕はコドモの頃から、予定調和的な物事が性に合わなかった。予め答えがあること、誰が見てもそうだろう!というものは、実につまらない。進化するロックミュージックもまさに、予定調和とは真逆の世界だよね。常に新しいリフが出てきたり、妙に引っかかる音があったり。そうきたかーっていうソロがあったり。
結局、人生も仕事もそうだなあと感じます。仕事も人生も要は「誰をロックするか」「誰に揺さぶられるか」「自分をロックできているか」だと思う。そして、その中から互いに「そう楽しみ、どんな活路を見出すのか」を試行錯誤しながら可能性を探しつつ、ときにぶち壊しながら(笑)、即興の関係性で新しい何かを創りあげて行く。 仕事も音楽もこのプロセスが面白いんだよね。これは、音楽が僕に教えてくれた人生哲学の一つであり、いつもそういう働き方・生き方を体現できたらいいな、と思っています。
昔話だけど、中3のとき学内にロックギター同好会をつくったら、クラシック音楽信奉者の音楽教師に潰されそうになったことがあります。 40年前はまだロックが不良や非行と直接結び付くイメージだったんだろうね。 教師が僕に直接言ってくるならまだしも、下級生に「安藤と一緒にロックなんかやっていると内申点を下げるぞ」的な圧力をかけていることを知って、ブチ切れましたね(笑)。青かった僕は無謀にも職員室に怒鳴り込みをかけた。「ロックをナメるな!」ってね (笑)。あれは自身の中では強烈な原体験となったし、ずっとそれから現在に至るまで、僕の中の譲れない信条みたいなものになっている気がします。

はたミュー:安藤さんの世代で育児に前向きだった男性は珍しいと思いますし、転職も多いですよね?やはりロックが影響しているのでしょうか?
安藤さん:結婚して3人の子を育てながら9回の転職、そしてNPOで起業。激動の人生のように言われるけど僕の中では音楽でいう「転調」みたいなもの。転職にしても、ミュージシャンがいろいろなバンドを渡り歩くみたいなものだ、と思っています。
特におもしろいのは、音楽的成長と人間的成長は“同期”していることが、実感として何となく分かって来るんです。自分が演っていても、他人の演奏を聴いていてもね。この前、ヴァン・ヘイレンをステージで見たとき、音が大人になってる!って感じたんだよね。僕自身もバンド演っていて昔は自分が弾くことに夢中だったんだけど、最近は人の音をちゃんと聴けるようになった。これは「自我」が何より勝っていた若い頃では、まだ獲得できなかった感受性の一つだと思う。
あとは、ミック・ジャガーとか、ポール・マッカートニーとかを見ていても、つくづくいい歳の取り方をしている。チクショー負けてられないなあって思う。 彼らが著名ミュージシャンだからっていう訳ではなく、まさに彼ら自身の生き方そのものが音楽に現れている。だから僕はプロのミュージシャンじゃないけれど、自分の仕事、自分のフィールドで輝きたいなって思うんです。
たぶん音楽の本当の面白さってそういうところにある。僕はロックから人生で大切なこと学べた。音楽自体が何かを解決や達成してくれる訳ではないけれど、少なくとも人が生きていくうえで、パワーに繋がることは確かだと思う。 だからすべての子ども達にも音楽好きになってほしいんだよね。
音楽は「祭り囃子」。元来、生活の日々の“営み”そのものに寄り添って来た訳だし、ファッションとか添え物じゃなく、明日を楽しく生きるために音楽ってある。特に、昨今のように閉塞感を感じる時代にこそ、音楽の力は必要なはずです。
はたミュー:音楽で社会はより良くなっていくと?
安藤さん:そうですね。まず、「社会をこう変えたい」という目的があって、それを伝えるための手段・方法として音楽を使い、音楽の力で共感の輪をひろげる。かつても「反戦ソング」や「USA for Africa」なんかはあったけど、日本のメジャーなミュージシャンはそういう活動の形がなかなか取れないし、限られた人はやっているけど大きく報道もされない。でもそれが民間のNPOレベルだったら日常的に、草の根的に出来ると思った。まだ多くの人たちが知らない社会問題を顕在化させたり、「いまそこにある危機」を気づかせるためのメッセージを届ける音楽を演ってるグループ。それを、“ソーシャル系バンド”と呼びたいと思います。
社会に自分の声を上げて行くためのツールとしてのバンド。本業しながらでも楽しくライフワークとして一生続けて行けるし、「かつてバンドマンだった親父達」も上司の顔色ばかり窺ってちっちゃく生きるんじゃなくて、もう1回仲間とバンド組んで、アンプにシールドぶっこんで、ハイボリュームでギターかき鳴らして、本当の自分を取り戻す時間があってもいいんじゃないかと思う。付き合いゴルフより、飲み屋で同僚と毎晩くだ巻いているよりも、よっぽど楽しいと思うんだけどね。
で、そのときに必要なのは単なる「自己満足」「ストレス解消」じゃなくて、「ソーシャル的発信」が欲しいね。社会を変えるなんて大袈裟なテーマじゃなくても、子どもたちなど身近にいる誰かを笑顔にできる、生きるチカラを授けるような音楽をやって欲しいと思う。
もちろん音楽自体が問題を解決してくれる訳ではないんだけど、講演で言葉を尽くすよりメロディーや歌詞とともにその人の心にしっかり残るだろうし(どこかで同じ曲を聴けば思い出してくれるだろうし)、その人が支援者としてアクションを起こすときに背中を押すような効果があると思ってます。かつて「タイガーBAND」で児童養護施設から呼ばれて演奏したとき、子ども達が笑顔になってくれたときには、「音楽やっていてよかった」と心から思えました。 音楽が放つメッセージだけでなく、仲間とバンドを楽しんでいる姿を見てくれて、子どもたちも「大人って楽しそうだな」「仲間と一つになるって、なんかいいな」って感じてくれたらいいね。
音楽の力が発揮されて、生きる実感や手応えを改めて感じられる。一人一人が、自分の中に眠る魂のメッセージを呼び戻すことができる。そういう本来のあり方に、音楽自体が立ち返って行く。 そのための一つのきっかけに、“ソーシャル系バンド”がなっていけたらいいなと思いますね。活動が有機的にネットワーク化されていけば、いずれ「バンドエイド」みたいな大きなイベントも実現できるかもしれないしね。
はたミュー:今後のビジョンや夢はありますか?
安藤さん:はい。まず、今の一連の活動は今後もライフワークとして継続できればいいなと思っています。 あと、60歳になったら「ソーシャル・ロックカフェ」をやりたい。学校の校門の前とかに出店して、子ども達もフラッと立ち寄れるような。 僕はマスターをやりながら、お客さんのために特別な一曲をかける役目。例えば勉強や学校生活に行き詰まった奴には、「これ聴いてみろ!クイーンって言うんだぞ」なんて解説付きで、パンチの効いた曲を。昼間は家事に育児に疲れたママやパパに癒しの珈琲とグッドミュージックを。夕方は学校の先生、夜は仕事終わりのサラリーマンにブルースをかけながらビールでも飲みながらおしゃべりしたいですね。 皆の駆け込み寺でありつつ、地域コミュニティのたまり場でもあり、多世代の伝承の場にもなれたらと。「あそこの店のオヤジと無駄話するの、SNSやっているより面白いぞ!」っていう具合になればいいね(笑)。
音楽は僕にとって「朝飯」みたいなもの。毎日のスタートを切るものであり、食べないと元気が出ない。ちなみに感覚的には、聴く音楽はご飯。演る音楽は、「ビールを飲む」みたいな感じです(どうせ飲むなら楽しく!)。 若い頃なんかは、失恋やら失敗やら、落ち込んだときの“よすが”的な存在。いつも身近にあって、僕に力をくれるものです。 いずれにせよ音楽はどんな時も、僕にはなくてはならないものだったことは確かで。風呂入るときでもいつでも、音楽が鳴ってないとだめ。常に聴いてないと、自分でいい演奏もできないしね。
はたミュー:次世代の子どもたちに「音楽」をどう伝えていきたいですか?
安藤さん:例えば自分の子どもは僕のCDを聴いたりしない。僕は10代の頃、いつも兄貴のレコード棚から引っ張り出しては聴いていたし、週末レコード屋に行くことが普通の休日の過ごし方だった。お目当ての外タレBANDが来日したときはプレイガイドに友だちと徹夜で並んだりとか、来日前は試験勉強もそっちのけでそのバンドの曲を一所懸命コピーしたり。(笑)。
昔と今をただ比較することに意味は無いですが、いまや音源はネットですぐ手に入るし、わざわざ外に音楽を聴きに行く、探しに行く習慣も無いんだよね。音楽の原体験も持ちづらい時代になってしまった。僕が10代だった70年代の音楽体験は、そのものが、文化・カルチャーを知ることで、社会を覗き見る窓としての役目を持っていたんですよね。だから、10代のとき音楽を通じて知ったこと体験したことは、今の自分自身にも確実に活きている。
という訳で、僕が次世代に伝えられることがあるとするなら、子ども達にとっての音楽も、娯楽・エンタメを超えてもっと生活に根ざしたものになるといいなあ、ということ。子ども時代の僕が、ロックから「生き方の軸」を教わったようにね。
自分の子ども達にも、「音楽をやるのは特別なことじゃないんだ」ってこれからも言い続けたい。余談ですが、うちの高校生の娘は吹奏楽部でドラムをやってます。娘が妻のお腹にいるときから、毎日ビートの効いたロックやソウルミュージックを聴かせてたからね。(終)

※このインタビュー記事は、2014年に「はたらくミュージシャン協会」のサイトに掲載になったものを再録したものです。